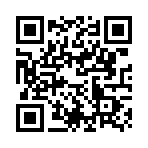2009年01月20日
ふと、農業について
東京、吉祥寺から 大分に引っ越してきた年、新聞で新規就農事業ってのを見ました、
そして応募、参加させてもらったことがあります、
内容は月何回か日曜日に三重町の県農業試験場にて農業の実践をしてみるという内容、当初は家族で参加してワイワイと楽しくしておりました、そのうち、奥様、お子様はリタイヤ、私だけで参加、同時期に参加されたご家族連れの方も、姿をみることが少なくなりました。
そんな中で元気一杯だったのが定年退職された60前後の面々でした、当時40前だった私なんかよりもはるかにアクティブだったです。
その時の話題のなかで、皆さんは本気で就農されようと思っているのに、県の支援対象には年齢制限がある、っていうことがありましたね、確かに県からすると、若い人の農業参加、定着をイメージしていたのでしょう、しかし、実践してみて初めてわかる農業の大変さ、リスク、今の若い人はほとんど選択しないでしょうね、その点、定年された方々は ある意味マイペースかつ、自分なりのイメージを農業にたいしてお持ちなんです、いわゆる自給自足的な発想っていうのでしょうか、農業を間違いなく楽しもうとされているんですね、この姿勢、間違いでないです、結果としてその後も畑を借りて続けられているかたが多かったです。
私は というと、実習期間が終わって一応、県の農業新規就農支援の窓口に相談に伺いました、そして最初に言われたこと、農業じゃ当初は食えません、500万以上貯蓄してから始めるように、とアドバイスされました。
え、えっ?
ちょっと、驚きだったですね、
どこが就農支援?
確かに現実はそうかもしれませんが、そんなこといわれて、はたして新規に参入する人いらっしゃいますかね?
農地についても別に斡旋してくれる訳でもなく、(厳密には農地取得には農業委員会の承認が必要でその他、諸条件をクリヤした上でないと難しいと教えていただきました)こちらは就農支援というぐらいだから、どこか格安に農地を貸してもらえたり、なんてのをイメージしていたので、正直、農業を新規に始めることは今の自分では無理が多い、という結論にもっていくしかないようでした、これって私にかぎったことじゃないんじゃないでしょうか?
形ばかりの政策、仕組みになっていて、実現する前提ではないのでは? と思わざるを得ないです。
ま、こんな現状の支援策でも、いや支援策に関係なく、新規就農されている方はいらっしゃるのですから、私について言えば そのタイミングにあらず、ということなのでしょう。
そんな経緯から10年以上過ぎ、今改めて想います、土に触れること、種を蒔くこと、作物を育てること、収穫すること、やっぱ あこがれですね、いつかはきっと、なんてね。

そして応募、参加させてもらったことがあります、
内容は月何回か日曜日に三重町の県農業試験場にて農業の実践をしてみるという内容、当初は家族で参加してワイワイと楽しくしておりました、そのうち、奥様、お子様はリタイヤ、私だけで参加、同時期に参加されたご家族連れの方も、姿をみることが少なくなりました。
そんな中で元気一杯だったのが定年退職された60前後の面々でした、当時40前だった私なんかよりもはるかにアクティブだったです。
その時の話題のなかで、皆さんは本気で就農されようと思っているのに、県の支援対象には年齢制限がある、っていうことがありましたね、確かに県からすると、若い人の農業参加、定着をイメージしていたのでしょう、しかし、実践してみて初めてわかる農業の大変さ、リスク、今の若い人はほとんど選択しないでしょうね、その点、定年された方々は ある意味マイペースかつ、自分なりのイメージを農業にたいしてお持ちなんです、いわゆる自給自足的な発想っていうのでしょうか、農業を間違いなく楽しもうとされているんですね、この姿勢、間違いでないです、結果としてその後も畑を借りて続けられているかたが多かったです。
私は というと、実習期間が終わって一応、県の農業新規就農支援の窓口に相談に伺いました、そして最初に言われたこと、農業じゃ当初は食えません、500万以上貯蓄してから始めるように、とアドバイスされました。
え、えっ?
ちょっと、驚きだったですね、
どこが就農支援?
確かに現実はそうかもしれませんが、そんなこといわれて、はたして新規に参入する人いらっしゃいますかね?
農地についても別に斡旋してくれる訳でもなく、(厳密には農地取得には農業委員会の承認が必要でその他、諸条件をクリヤした上でないと難しいと教えていただきました)こちらは就農支援というぐらいだから、どこか格安に農地を貸してもらえたり、なんてのをイメージしていたので、正直、農業を新規に始めることは今の自分では無理が多い、という結論にもっていくしかないようでした、これって私にかぎったことじゃないんじゃないでしょうか?
形ばかりの政策、仕組みになっていて、実現する前提ではないのでは? と思わざるを得ないです。
ま、こんな現状の支援策でも、いや支援策に関係なく、新規就農されている方はいらっしゃるのですから、私について言えば そのタイミングにあらず、ということなのでしょう。
そんな経緯から10年以上過ぎ、今改めて想います、土に触れること、種を蒔くこと、作物を育てること、収穫すること、やっぱ あこがれですね、いつかはきっと、なんてね。

Posted by sakapa at 14:56│Comments(15)
この記事へのコメント
この不況は日本の食糧自給率を上げる
チャンスでもあるんですけどね
チャンスでもあるんですけどね
Posted by ちょもり☆ at 2009年01月20日 14:59
at 2009年01月20日 14:59
 at 2009年01月20日 14:59
at 2009年01月20日 14:59いっそのこと、農業の会社を作ったらどうかと思います。国営だったら何となく無駄がありそうなので、民営で。もちろん、現存する農家を保護することが第一です。その上で、特に自給率が低い大豆のようなものを作り、そこで社員として働くような形はどうかと思っています。国産大豆の安全で美味しい豆腐が作れるとなると企業にもメリットがあると思うのですが。
Posted by せさみん at 2009年01月20日 15:20
↑せさみんさんが言われてることを実際されている方々がいらっしゃるようです。
先日、テレビで放映されてました。10人程度の会社だったでしょうか。
高齢で畑を作れなくなった人たちの畑を安く借りて、皆でお金を出し合い、大きな
農機を購入し、大豆や小麦を作るところから始めたそうです。現在の国産にこだ
わる流れに乗って、かなり伸びてきてるそうです。
一応、代表取締り役の方はおられましたが、利益はある程度平等に分けられて
いるようで、これからの農業はこんな感じに進化していくのかもしれません。
先日、テレビで放映されてました。10人程度の会社だったでしょうか。
高齢で畑を作れなくなった人たちの畑を安く借りて、皆でお金を出し合い、大きな
農機を購入し、大豆や小麦を作るところから始めたそうです。現在の国産にこだ
わる流れに乗って、かなり伸びてきてるそうです。
一応、代表取締り役の方はおられましたが、利益はある程度平等に分けられて
いるようで、これからの農業はこんな感じに進化していくのかもしれません。
Posted by Coco at 2009年01月20日 15:47
at 2009年01月20日 15:47
 at 2009年01月20日 15:47
at 2009年01月20日 15:47よし、閉店している店舗を整地して竹町に畑でも作りますかい!
Posted by つね at 2009年01月20日 16:09
at 2009年01月20日 16:09
 at 2009年01月20日 16:09
at 2009年01月20日 16:09アグリー施策にアングリー!
こんな無策で無政府状態がいつまで続くことやら・・・
そのうち国民はハングリーになってしまうやんか!
こんな無策で無政府状態がいつまで続くことやら・・・
そのうち国民はハングリーになってしまうやんか!
Posted by タロー at 2009年01月20日 16:36
お邪魔します。
国や県というお上の沙汰を見ると・・・・
いろいろやっていますよね。
補助金にぶら下がりおいしい思いをしている人もいるようです。
農商工連携事業事例
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/MT88/01.html
十人十色の価値観がある中で,行政やお上にぶら下がることなく,
面白く愉快に農業をやっている人もたくさんいるようです。
つねさまが言っているように竹町の畑を造るとか!
じゃん公オリジナルの農商工連携できるんじゃなんでしょうか♪♪♪
東京では都心の真中で農機具を完備したレンタル畑が大流行だそうです。
国や県というお上の沙汰を見ると・・・・
いろいろやっていますよね。
補助金にぶら下がりおいしい思いをしている人もいるようです。
農商工連携事業事例
http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/MT88/01.html
十人十色の価値観がある中で,行政やお上にぶら下がることなく,
面白く愉快に農業をやっている人もたくさんいるようです。
つねさまが言っているように竹町の畑を造るとか!
じゃん公オリジナルの農商工連携できるんじゃなんでしょうか♪♪♪
東京では都心の真中で農機具を完備したレンタル畑が大流行だそうです。
Posted by ラボ爺 at 2009年01月20日 17:24
はじめまして、
野菜工場というのが新しい試みでなされています。
昨年の派遣切り、輸入物の安全性の問題で、
今までは「野菜工場」は工場扱いで、工場設立の法律に従っていたため、
あちこちに作ることができなかったそうです。
この春にはその法律が見直されて、
畑扱いにされるとか。
そうなると町中でも無農薬のミニ「野菜工場」が作れるようになるかも?
野菜工場というのが新しい試みでなされています。
昨年の派遣切り、輸入物の安全性の問題で、
今までは「野菜工場」は工場扱いで、工場設立の法律に従っていたため、
あちこちに作ることができなかったそうです。
この春にはその法律が見直されて、
畑扱いにされるとか。
そうなると町中でも無農薬のミニ「野菜工場」が作れるようになるかも?
Posted by k at 2009年01月20日 21:00
農家は世襲制なので一応私も最低限の耕作を細々と・・・
耕したい方はいくらでも場所はお貸ししますよー
耕したい方はいくらでも場所はお貸ししますよー
Posted by ペーター at 2009年01月20日 21:32
ちょもり☆さん>
そー、
政治がやれること、今ぐらい沢山ある時期も珍しいのにねー、
どうしたもんでしょ?
せさみんさん>
いろんな切り口で国内農業は可能性があると思います、今の政権には見えていないようですが。
CoCoさん>
そういうグループがどんどん増えるといいのですがね、国の制度が追いついていない、というか現状が全く見えていないんです、きっと。
つねさん>
そやね、いっそアーケードの半分ぐらい畑にしたらハウス栽培みたいになったりしてね。
ラボ爺さん>
なんか、農業分野、介護分野、政府や自治体の現状把握能力が遅れていますわー、現場を重視すれば解かることなんですが,縦割り行政、1本槍ですからねー。
そー、
政治がやれること、今ぐらい沢山ある時期も珍しいのにねー、
どうしたもんでしょ?
せさみんさん>
いろんな切り口で国内農業は可能性があると思います、今の政権には見えていないようですが。
CoCoさん>
そういうグループがどんどん増えるといいのですがね、国の制度が追いついていない、というか現状が全く見えていないんです、きっと。
つねさん>
そやね、いっそアーケードの半分ぐらい畑にしたらハウス栽培みたいになったりしてね。
ラボ爺さん>
なんか、農業分野、介護分野、政府や自治体の現状把握能力が遅れていますわー、現場を重視すれば解かることなんですが,縦割り行政、1本槍ですからねー。
Posted by sakapa at 2009年01月21日 04:16
at 2009年01月21日 04:16
 at 2009年01月21日 04:16
at 2009年01月21日 04:16kさん>
コメント有り難うございます。
そうなんですかー、
そういえば大分は野菜工場,何箇所かありましたね、
野菜類はすぐ収穫できるから街中でミニ菜園なんかのパッケージもよいですね。
ペーターさん>
いいねー、
もうちょっと近所だったらすぐに貸してもらうんやけどなー。
コメント有り難うございます。
そうなんですかー、
そういえば大分は野菜工場,何箇所かありましたね、
野菜類はすぐ収穫できるから街中でミニ菜園なんかのパッケージもよいですね。
ペーターさん>
いいねー、
もうちょっと近所だったらすぐに貸してもらうんやけどなー。
Posted by sakapa at 2009年01月21日 04:23
at 2009年01月21日 04:23
 at 2009年01月21日 04:23
at 2009年01月21日 04:23耕作放棄地は、けっこうあると思いますよ。
今、お隣さんに人がもどってきて。
農業しようとしていますが。
さ~て、いつまでもつでせう。
今、お隣さんに人がもどってきて。
農業しようとしていますが。
さ~て、いつまでもつでせう。
Posted by asu at 2009年01月21日 23:39
at 2009年01月21日 23:39
 at 2009年01月21日 23:39
at 2009年01月21日 23:39asuさん>
耕作放棄されてる土地、大分近郊でよく見かけます、
その辺の需給情報をネットで繋げればプラスになることもあるんじゃないのか、なんて思ったりもします。
耕作放棄されてる土地、大分近郊でよく見かけます、
その辺の需給情報をネットで繋げればプラスになることもあるんじゃないのか、なんて思ったりもします。
Posted by sakapa at 2009年01月22日 11:34
at 2009年01月22日 11:34
 at 2009年01月22日 11:34
at 2009年01月22日 11:34大分活性化宣言で活躍するケンジさんのような方が
橋渡し役として農と商を繋げるとか!?
一見,徒労と思われる地道な活動がとても重要ですよね。
お上が蔑ろにしてきた分野です。。。
山形での事例ですが・・・・
http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020020/mm_bk_data/mm_spcial/power_No79.html
http://sato-tsunokawa.cocolog-nifty.com/system/index.html
橋渡し役として農と商を繋げるとか!?
一見,徒労と思われる地道な活動がとても重要ですよね。
お上が蔑ろにしてきた分野です。。。
山形での事例ですが・・・・
http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020020/mm_bk_data/mm_spcial/power_No79.html
http://sato-tsunokawa.cocolog-nifty.com/system/index.html
Posted by ラボ爺 at 2009年01月22日 13:03
ラボ爺さん>
そうですね、他県の取り組みも参考にはなるところもありますが、根本がまだつかみきれていないようにも見えます、大分ではまず現場の情報集約からスタートかもしれませんね。
そうですね、他県の取り組みも参考にはなるところもありますが、根本がまだつかみきれていないようにも見えます、大分ではまず現場の情報集約からスタートかもしれませんね。
Posted by sakapa at 2009年01月23日 15:39
at 2009年01月23日 15:39
 at 2009年01月23日 15:39
at 2009年01月23日 15:39農地を貸すには何かとややこしいのです。
特に基盤整備などされた「第一種農地」に関しては
貸し借りする場合にもお上の承諾が必要です。
現状の「農」の状態と乖離も甚だしい農政を憂います。
まっ〇〇も政治〇も農民から搾取してるだけですからね。
知事がパーッと取り組めば色々な難関は取り払えるのですが・・
まぁ農を知らない人には無理だなぁ
特に基盤整備などされた「第一種農地」に関しては
貸し借りする場合にもお上の承諾が必要です。
現状の「農」の状態と乖離も甚だしい農政を憂います。
まっ〇〇も政治〇も農民から搾取してるだけですからね。
知事がパーッと取り組めば色々な難関は取り払えるのですが・・
まぁ農を知らない人には無理だなぁ
Posted by ペーター at 2009年01月23日 19:55